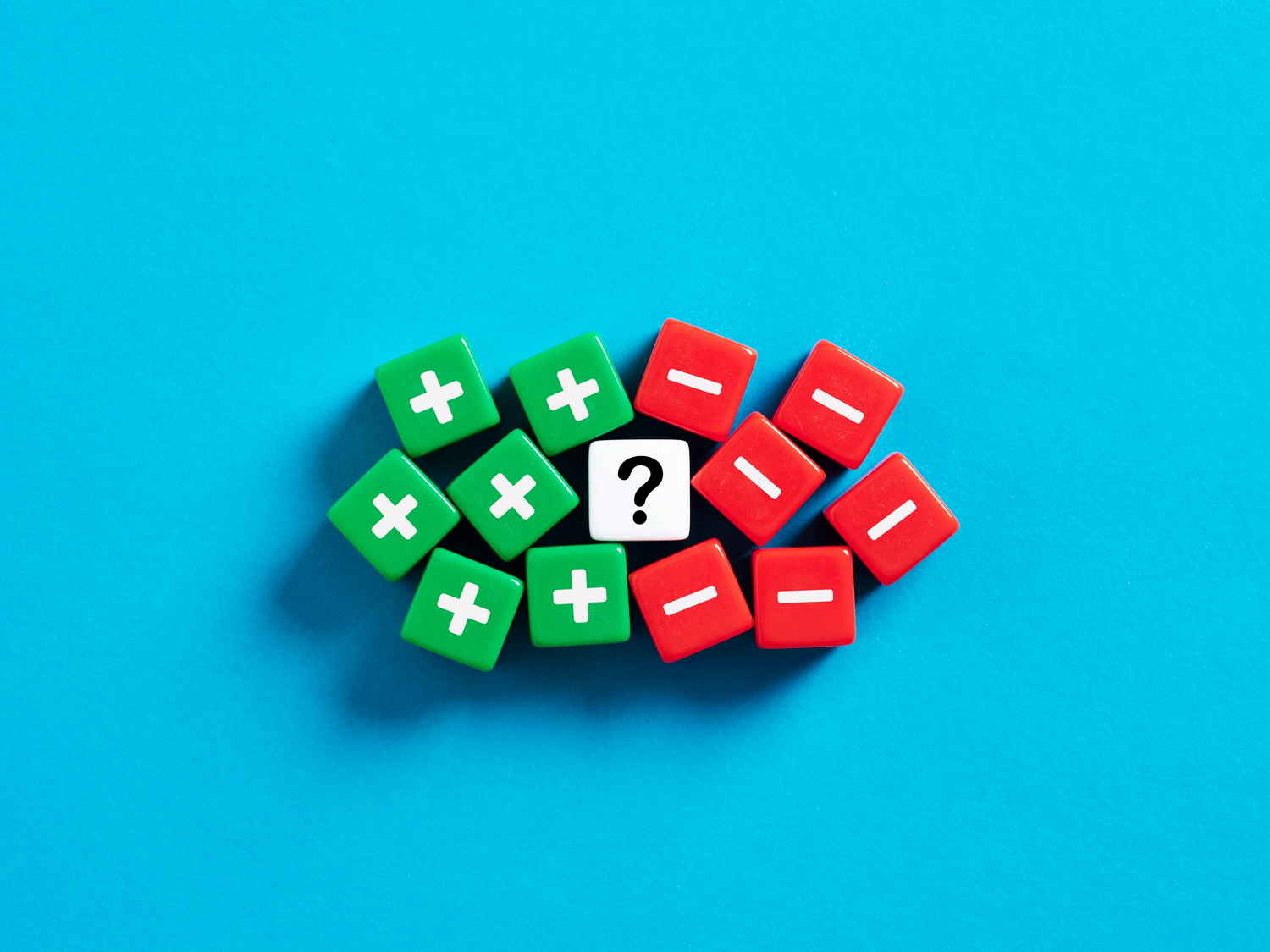2025年8月10日
電動車椅子の特徴や用途、今後の可能性を解説
運転者の「足」として重要な役割を果たしている車いす。従来は腕の力を使い自力で、もしくは介助者が押すことで前進する「手動車いす」が主流でしたが、近年「電動車いす」の利用者が増えている傾向にあります。今回の記事では電動車いすの特徴や用途、次世代型モデルの開発状況など…さまざまな角度からモビリティの魅力や特徴を紐解いていきたいと思います。
読者の関心度
★★★★☆
4
※ 各読者がページに費やす時間によって決まります。
片倉 好敬
Katakura Yoshitaka
アベントゥーライフ株式会社
代表取締役 兼 CEO
電動車いすとはどんなモビリティ?
電動車いすは「パーソナルモビリティ」の一種に分類される乗用具です。パーソナルモビリティは、街中での近距離移動を想定した1~2人乗り電動コンセプトカー全般のこと。車いすは、身体の不自由な方や高齢者の日常生活の移動を支援するモビリティですが、腕の力を使い自力で動かすか、介助者に押してもらう必要があります。
自走型の場合は力が必要なので体力を使います。長距離の走行はしんどいと感じることも…。自走できない場合は「押してくれる人」ありきの移動となるため、「ちょっとそこまで走りたい」という場合でも誰かに手伝ってもらう必要があり、不安やストレスの原因になります。また、介助者の押す力も必要なので長距離は不向きかつ坂道、目の粗いアスファルトでの走行は危険も伴います。
電動車いすの多くはジョイスティックレバー(1本の棒を前後左右に倒すことで、前進・後進、右折・左折を行なう装置)の操作で進みたい方向へ移動できるので、弱い力でも自分で動かすことが可能です。重量と安定感もあるので安心して使えますよ。
電動車いすにはどんな種類がある?
電動車いすは大きく分けて3つの種類に分類されます。
①ジョイスティック型電動車いす
最もオーソドックスな電動車いすです。前述したように、ジョイスティックレバーを操作することで走行します。レバーの操作が困難な方向けにスイッチ入力や多様入力コントローラ・入力装置のオプションを用意しているメーカーもあります。
②簡易型電動車いす
手動車いすに、モーターやバッテリーなどの電動機能を取り付けたモビリティを指します。電動と手動の切り替えが可能という点が大きな特徴です。手動に切り替えれば普通の手動車いすとして使えます。万が一バッテリー切れを起こしても手動操作で動くのは嬉しいポイントです。さらに折りたたみ可能な設計が多く、車やタクシーに積むこともできますよ。形状は手動車いすと類似しています。
③アシスト型電動車いす
手動車いすを介助者が押す場合、介助する側にも負担がかかります。車いすを押した経験のある方はお分かりかもしれませんが、体重のある大人を乗せた車いすを押すのは結構大変です。特に坂道や凸凹のある道は力が必要ですし、車輪がうまく動かず危険な目に合う場合も…。
アシスト型電動車いすであればモーターの補助があるので、凹凸のある地面や上り坂でもスムーズに押すことができます。下り坂では自動でブレーキがかかるので安心です。介助者の負担を軽くすることができますよ。
電動車いすと似ている?「ハンドル型電動車いす」との相違点とは
ハンドル型電動車いすは、別名「電動カート(シニアカー)」とも言われているモビリティで、ハンドル操作による走行が可能な点が特徴です。主に足腰が弱い高齢者の移動手段として利用されています。
スクーターのような見た目で買い物かごが付いているものが多く、普通の車いすとは似て非なる存在です。車いすであれば屋内施設や電車やバスなどの公共交通機関への乗り入れが可能ですが、ハンドル型電動車いすは屋外利用のみを想定している点も大きな違いだと言えるでしょう。
電動車いすのメリット、デメリットをそれぞれ解説!
電動車いす最大のメリットは手押しではなく自動で操縦ができる点です。体力を消耗せず、自分の意思で移動できるのは利用者にとって嬉しいポイントではないでしょうか。(※介助者が押すアシスト型を除く)
最近は街や屋内施設のバリアフリー化も進んでおり、車いすでも快適に移動できる場所が増えていますし、電車やバスなどの公共交通機関に車体ごと乗せられるのも便利です。
一方、バッテリー式のため、ジョイスティック型の場合は充電が切れると走行不能になってしまう点はデメリットです。フル充電の場合、10㎞前後の走行が可能ですが、人によっては少ないと感じる方もいるかもしれません。
また、バッテリーは消耗品のため、1~3年程度で交換が必要です。メンテナンスにやや費用がかかるのは難点の一つと言えるでしょう。
電動車いすの交通ルールは?道路交通法上の分類とは
電動車いすは、道路交通法上、歩行者として扱われています。交通ルールは歩行者同様であり、歩行者と同じ速度で通行することが定められています。歩道があれば歩道を、ない場合は右側の路側帯を通行します。
なお、ハンドル型電動車いすも、電動車いすと同様の扱いです。車体の大きさは長さ120㎝、幅70㎝、高さ120㎝以内と定められており、毎時6㎞以上の速度を出せない車両であることが条件です。
参考:警察庁webサイト>[電動車いすの安全利用について|警察庁Webサイト](https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/e_wheelchair.html)
電動車いすに座った時の高さは、小学生低学年児と同じくらいの身長になります。そのため利用時の視線は自然と低くなり、視野も狭くなります。(※身長165㎝の女性が着座した場合の高さが120㎝なので、背の低い方であればさらに視界が悪くなります。)路側帯を走る際は、路肩に停止している車両や障害物にも注意が必要です。
便利な機能が年々増えている電動車いすですが、街中での通行には一定の不便や困難も伴います。歩道や通路をはみ出す自転車の駐輪や歩きスマホは車いすユーザーにとって恐怖の対象になります。一方電動車いすは歩行者から見ると「強い存在」 ともなりうるので、歩行者・利用者双方が交通ルールを守って安全に通行することが大切です。
電動車いすを利用するのはどんな人?
電動車いすを利用するのは、主に高齢者と身体機能に障害がある人です。
下肢などの切断、脳血管障害。脊髄損傷、脳性麻痺、進行性筋萎縮、リウマチ性疾患などにより、下半身の機能が失われ、自力での歩行が困難になった場合でも車いすがあれば移動の自由が叶います。また、一時的な怪我や病気により使用するケースも多々あります。
参考:[さまざまな人がいます ともに生きる社会をめざして交通バリアフリーを学ぼう](https://www.bfed.jp/teach/people/people_b.html)
車いすユーザーを見かけたら、思いやりを持った行動をすることが大切です。
車いすには配慮と思いやりを…優先エリア、占領していませんか?
公共交通機関に乗り入れることも多い車いす。駅や電車・バスには車いすユーザーを想定したさまざまな工夫が散りばめられています。
車内にある車いすやベビーカーの優先スペースは、車いす(※ベビーカー含む)ユーザーが車体ごと入れるように優先席近くに設けられた場所です。床や壁に描かれた車いすのマークを見たことがある方は多いと思います。
しかし、「壁に寄りかかれるのが楽だから」と関係ない人が使用しているケースが多いのが現状です。混雑時など難しいケースもあると思いますが、優先スペースはできる限り空けておくと良いでしょう。
また、駅構内や商業施設に設けられた優先エレベーターも常に混雑しており、本当に乗りたい人がなかなか乗れず立ち往生している姿をよく見かけます。
優先エレベーターの対象者は「移動手段が限られている人」なのでお互いが気持ちよく利用できるよう、譲り合いと思いやりの気持ちを持つことが大切です。
電動車いすにはレンタルという選択肢も…!介護保険は使える?
生活の幅を広げることが期待できるとても便利なモビリティですが、購入するには高額な費用がかかる電動車いす。
介護保険を利用して、少ない自己負担でレンタルできることをご存じでしょうか?
介護保険を申請しており、なおかつ要介護度が2以上であれば1割負担での利用が可能です。以下表のとおり、自立歩行が困難なケースの多くが「要介護2」以上に認定されます。
| 要介護1 | 基本的に日常生活は自分で送れるものの、身体能力や思考力の低下がみられ、日常的に介助を必要とする。 |
| 要介護2 | 食事、排泄などは自分でできるものの生活全般で見守りや介助が必要。 |
| 要介護3 | 日常生活にほぼ全面的な介助が必要。 |
| 要介護4 | 自力での移動ができないなど、介助がなければ日常生活を送ることができない。 |
| 要介護5 | 介助なしに日常生活を送ることができない。コミュニケーションをとることが困難で、基本的に寝たきりの状態。 |
(参考:[【要介護認定区分早わかり表付き\!】理解できてる?要支援と要介護の違いの基準とは?|ベネッセスタイルケア](https://kaigo.benesse-style-care.co.jp/article/knowledge/beginner/shienkaigo))
また、電動車いすの介護保険適用条件は「要介護2」以上の方と定められていますが、一部例外もあります。「日常的に歩行が困難」「日常生活における移動の介助が特に必要」と医師による診断を経て認められた場合には、「意見書」があれば要介護1以下でもレンタルすることが可能です。
介護保険を使い、レンタルする場合の月額必要は約2,000~3,000円。電動車いすを購入する場合が20~40万円程度の費用がかかると考えると、割安で利用できることが分かります。
しかし長期的な目線で考えると購入するほうが長い目で見ると良いこともあるので、どのくらいの期間使うことになるか想定して検討することをおすすめします。
階段昇降ができる「次世代電動車いす」をご存じですか?
モビリティ製品の研究開発を行うスタートアップ企業 「LIFEHUB株式会社」が、2025年3月に次世代の電動車いす型パーソナルモビリティ 「[AVEST Launch Edition](https://sdgsmagazine.jp/2025/04/04/15024/)」の先行予約(限定50台)を開始したことをご存じでしょうか。
平地と階段、いずれの移動にも対応可能な電動車いすは、とても珍しく画期的。フル充電での走行距離は40km、重量は世界最大の95kgという車いすの概念を覆す商品が開発されました。価格は165万円と、軽自動車1台分と同等です。
従来、車いすで電車に乗る際はスロープ設置など、駅員の補助が必要でしたがその必要もなくなり、階段や段差も乗り越えることができるので移動のハードルが大幅に下がります。
今後は「エスカレータ昇降機能」を実装した次期モデルの販売も検討中とのこと、もし実現すれば、世界初のエスカレータ対応車いすモビリティが誕生します。
SDGsのゴール達成に貢献する革新的な「次世代電動車いす」の動向にも注目が集まっているのです。
電動車いすを活用し、移動のQOLを高めよう!
移動の不便を軽減する電動車いすはとても画期的なパーソナルモビリティであり、現在もさらなる開発が進んでいます。
車いす利用者が不自由なく移動の自由を叶えることができるように、交通利用者全員が思いやりと優しさを持った行動をすることが大切です。
社会がより暮らしやすく便利な時代になることを願っています。